はじめに
「話が長い」「結局なにが言いたいの?」
そう言われた経験、誰にでもあると思います。
でも、それは言葉が足りないからでも、知識が少ないからでもありません。
話の“形”ができていないからです。
話には「構造」が必要です。
構造とは、話の中に線を引いて順序をつくること。
たとえば、
- どこからどこまでが一つの話なのか(境界線)
- それぞれの話がどうつながっているのか(関係性)
この2つをはっきり示すだけで、相手はスムーズに理解できます。
逆に、線も順序もないまま話すと、
聞き手はあなたの話を頭の中で整理しながら聞かなければなりません。
結果、相手の思考エネルギーは「理解」ではなく「整理」に奪われてしまうのです。
構造化の3ステップ
構造化というと、なんだか難しそうに聞こえます。
けれど、実際にやることはとてもシンプルです。
たった3つのステップだけ。
1️⃣ 要素をわける
→ まず、話の中の内容を小さなかたまりに分ける。
2️⃣ 要素に名前を付ける
→ 分けたかたまりに「原因」「結果」「対策」など、わかりやすい名前をつける。
3️⃣ 要素を構造化する
→ 名前を付けたもの同士の関係を整理して、順番やつながりを見せる。
この3つを意識するだけで、
「話す」「書く」「説明する」など、どんな伝え方も一気にわかりやすくなります。
最初から3番目の“構造化”まで完璧にできる必要はありません。
まずは①と②――つまり「分けて、名前をつける」だけで十分です。
それだけでも、話は驚くほど伝わりやすくなります。
要素をわける
最初のステップは、話を要素ごとに分けることです。
これはまだ「構造化」や「名前付け」まではしていません。
ただ、話を一つの塊としてではなく、いくつかの小さな話に分けるだけです。
話がわかりづらい人の多くは、内容が1つの箱に混ざっています。
一文の中に複数のテーマが入り込み、どれが主題なのかが分からなくなるのです。
❌ 悪い例
最近、ちょっと仕事がうまくいかなくて、上司にもよく注意されるんですよね。
そのせいか集中力も落ちてて、家に帰っても疲れが取れないし、
同僚との関係も少しギクシャクしてきてる気がするんです。
あと、最近は業務の量も増えてきて、残業も多くなってて……。
たぶん色々なことが重なってると思うんですけど、もう何から改善したらいいのか分からなくて。
この話では、複数の話題が混在しています。
主題が移り変わるたびに文脈が切り替わり、聞き手はどの問題に集中すべきか判断できません。
さらに厄介なのは、どこからどこまでが一つの話なのかが分からないことです。
話が最後まで終わらないと要素を切り分けられず、聞き手は頭の中で
「ここは同じ話なのか、それとも別の話なのか?」と整理を続けることになります。
つまり、聞き手は内容を理解する前に、構造を推測する作業を強いられているのです。
この“理解しづらさ”の本質は、境界が見えないために整理が常に後追いになることにあります。
✅ 良い例
話がありまして、
1つ目が、最近仕事がうまくいかなくて、上司に注意されることが増えていること。
2つ目が、集中力が落ちていて、家に帰っても疲れが取れないこと。
3つ目が、同僚との関係が少しギクシャクしてきていること。
4つ目が、業務量が増えて残業が多くなっていることです。
多分いろいろ重なっていると思うんですが、まずはこのあたりを整理したいと思っています。
このように、話し始めは「話がありまして」や「相談なんですけど」などの
汎用的な一言で十分です。そこから先は、
「1つ目」「2つ目」「3つ目」と数字を増やしながら話題を区切るだけで、
聞き手は自然に話の全体像を把握できます。
まだ「課題」や「原因」などの名前付けはしていませんが、
話を分けるだけで情報が整理され、理解されやすくなるのです。
話を要素ごとに分けるだけで、相手の頭の中には複数の“箱”ができます。
あとは、その箱に中身を入れていくだけ。
話す側は同じ内容を伝えているのに、聞き手には整理されて届くのです。
要素をわけるとは、相手に“仕分け用の箱”を作ってあげること。
要素に名前を付ける
次のステップは、要素に名前を付けることです。
名前とは、つまり「ラベル」です。
「原因」「課題」「結果」「提案」など――それがあるだけで話が整理されます。
「〇〇が問題です」ではなく、
「問題は〇〇です」と言う。
この一言の違いで、聞き手の理解スピードが何倍にも上がります。
前者だと相手は話を最後まで聞かないと問題の話と分からないです。
後者だと相手は話を最後まで聞かずとも問題の話だと分かります。
✅ 良い例
仕事のパフォーマンス低下に関する相談です。
課題は、最近仕事がうまくいかなくて、上司に注意されることが増えていること。
原因は、集中力が落ちていて、家に帰っても疲れが取れないこと。
影響は、同僚との関係が少しギクシャクしてきていること。
現象は、業務量が増えて残業が多くなっていることです。
このように、話の全体に「名前(ラベル)」を付け、
それぞれの要素に「名前(ラベル)」を付けるだけで、
聞き手は「どの種類の話をしているのか」を瞬時に把握できます。
内容は同じでも、ラベルがあるだけで構造が見えるのです。
名前付けは、最初から完璧でなくても構いません。
間違っていても、後から付け直せば良いのです。
実際の話し合いの中では、議論を進める中で
「この名前の付け方で合っている?」という確認が何度も行われます。
それが内容の精査につながります。
たとえば、
「疲れが取れないことは“原因”ではなく、“結果”では?」という指摘があったとします。
すると、「集中力が落ちていること」と「疲れが取れないこと」は別の要素かもしれない――
と、構造が再整理されるわけです。
このように、名前を付けて、付け直していくプロセスそのものが“理解”の深化です。
ラベル化とは、相手の理解を助けるだけでなく、
話し手自身が思考を整理していく作業でもあるのです。
要素を構造化する
最後のステップは、要素同士の関係性を整理することです。
これは、「原因→結果→対策」や「現状→課題→解決策」といった“順序”を提示することです。
構造を先に見せるだけで、相手は地図を手に入れた状態で話を聞けます。
✅ 良い例
仕事のパフォーマンス低下に関する相談です。
課題、原因、影響、現象の順で話します。
課題は、最近仕事がうまくいかなくて、上司に注意されることが増えていること。
原因は、集中力が落ちていて、家に帰っても疲れが取れないこと。
影響は、同僚との関係が少しギクシャクしてきていること。
現象は、業務量が増えて残業が多くなっていることです。
次の一言で、聞き手の頭の中に4つの箱ができます。
これによって、4つの箱があり、その箱は並列であるとわかります。
「課題、原因、影響、現象の順で話します。」
あとはその箱に沿って話すだけで、情報は自然と整理されます。
おわりに
「伝える力」とは、言葉の巧さではなく、構造を見せる力です。
構造とは、相手に“パズルの完成図”を見せること。
どんなに複雑な話でも、構造があれば相手は迷いません。
🧩 構造化の4段階 ― パズルで考える
🔸 ⓪ 何もない状態
この段階では、相手に無数のパズルのピースを丸投げしているのと同じです。
ピースの数も形も不明で、相手は「どんなパズルを組み立てるのか」すら分かりません。
つまり、話の全体像も要素も一切見えない状態です。
🔹 ① 要素をわける
ここまでできると、少なくともピースの数がわかります。
相手は「何個の話題(要素)があるのか」を理解でき、整理の出発点が生まれます。
🔹 ② 要素に名前を付ける
さらに、ピースの形が見えるようになります。
「これは課題」「これは原因」「これは対策」といったラベルが付くことで、
相手はどんなピースがあり、どんな特徴を持つのかが分かります。
②までできれば、相手はパズルを解きやすくなります。
逆に、②までできていないと、相手は“ピース探し”から始めなければなりません。
🔹 ③ 要素を構造化する
最終段階では、ピースの数と形、そして組み立て方がすべて提示された状態です。
相手は“完成したパズル”を見ながら話を理解できる。
エネルギーは「整理」ではなく「理解」に集中し、思考がスムーズに進みます。
🧭 4段階のまとめ
| 段階 | 状態 | 相手の負担 |
|---|---|---|
| ⓪ | ピースを丸投げしている | 何を組み立てるかすら分からない |
| ① | ピースの数を伝えている | 全体の規模が分かる |
| ② | ピースの形を見せている | 組み立てやすくなる |
| ③ | 完成したパズルを共有している | 理解に集中できる |
💡 最後に
構造化とは、相手の思考エネルギーを守ること。
伝えるとは、情報を並べることではなく、パズルの完成図を共有することです。
構造を見せる人は、ピースの数・形・組み立て方を示す。
構造を持たない人は、中身も数も不明なピースを投げて「組み立てて」と言う。
構造とは、相手への思いやりなのです。


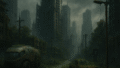
コメント