エンジニアのキャリアを考えるとき、「どの工程を経験しているか」は非常に重要です。開発工程には段階があり、それぞれに異なる責任と役割があります。最初から上流工程を担当できる人はほとんどおらず、多くの人は下流から順に経験を積み重ねていきます。この記事では、その一般的な流れと、本質的に求められる力について解説します。
スタート地点:試験(テスト)工程
多くのエンジニアが最初に担当するのが試験工程(テスト)です。
ここでは、他人が作ったシステムを触り、仕様通りに動くかを確認します。最初は「作る」よりも「理解する」仕事が中心で、プログラムの仕組みやバグの出方、修正の影響範囲を学ぶ最適なフェーズです。
この段階で重要なのは、「なぜこの不具合が発生したのか」を論理的に考える力。単なる作業ではなく、テストの裏側にある設計意図や開発者の考え方を読み取れる人ほど、次のステップに進みやすくなります。
第二段階:運用・保守または軽微な実装
次のフェーズは運用・保守です。
ここでは、既存システムの不具合修正や、軽微な機能追加を行います。テストで「気づく側」だった人が、ここで「直す側」になります。
このフェーズで求められるのは、読解力と再現力。
既存コードを理解し、どこを直せば影響が出ないかを見極めることが重要です。修正箇所が一見小さくても、他機能に影響する可能性があります。この「システム全体を俯瞰する視点」を持てる人は、自然と信頼を得て、より大きな改修や新規実装を任されるようになります。
第三段階:実装(開発の中心)
実装フェーズに入ると、ようやく「自分のコードで機能を形にする」領域に到達します。
運用・保守での理解が活きる段階であり、現場ではここで頭角を現す人が増えます。
ただし、実装ができる=設計ができるわけではありません。
実装とは設計の意図を具体的に形にする工程であり、設計が曖昧であれば、いくら技術力が高くても迷走します。そのため、ここで求められるのはコード力だけでなく、構造の理解力です。
第四段階:設計(システムを構築する思考)
実装が一定レベルに達すると、設計を任されるようになります。
ここで初めて「責任の重さ」を実感する人も多いでしょう。設計とは、開発チーム全員が同じ方向を向けるように構造とルールを定義する行為です。
ところが現実には、この設計を正しく行える人が少ない。
多くの現場では「なんとなく設計」「ドキュメントが形だけ」という状況が少なくありません。設計書が存在しても、実装と乖離しているケースも多く、結果として「設計に基づかない実装」が増えてしまいます。
設計で本当に求められるのは、「実装者が迷わない構造を設計する力」です。粒度を誤ると、実装者が自分で判断しなければならない箇所が増え、開発の品質がばらつきます。だからこそ、設計ができる人は希少であり、次の要件定義フェーズへ進む切符を手にします。
最終段階:要件定義(クライアントの意図を翻訳する)
要件定義は、顧客の言葉をシステムの言葉に翻訳する工程です。
ここに到達したエンジニアは、技術よりも「理解力」と「構造化力」が問われます。顧客の要望をそのまま実装に落とすのではなく、業務全体を見渡して本当に必要な要件を抽出する。これはもはや開発ではなく、設計思想の領域です。
まとめ:実装力が上流工程への入口
多くの現場では、設計や要件定義をしっかりできる人がほとんどいません。
ゆえに、「実装を正確にできる人」が上流工程を任されやすくなるのです。
実装とは、単にコードを書くことではなく、設計の意図を理解して形にする力。その延長線上に、設計と要件定義の世界があります。
つまりキャリアの流れはこうです。
試験 → 運用・保守 → 実装 → 設計 → 要件定義
どの工程も無駄ではなく、すべてが次のステップに繋がっています。
焦る必要はありません。小さな修正を積み重ね、設計意図を読み取る力を磨いていけば、自然と上流工程に呼ばれるようになります。

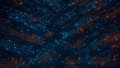
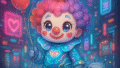
コメント